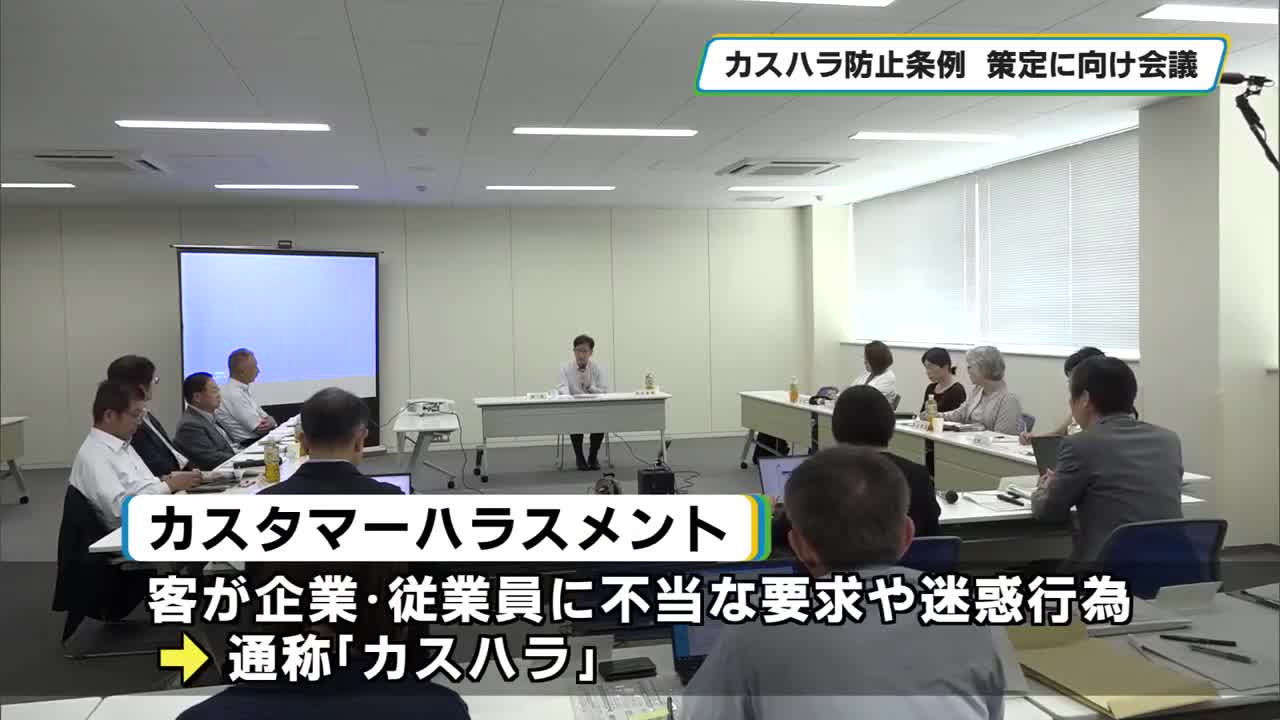栃木県のカスタマーハラスメント防止条例案 来年2月の県議会で提出を目指す 有識者会議の初会合
客が不当な要求や迷惑行為などを行う、カスタマーハラスメントが社会問題となる中、防止対策を検討するための有識者会議の初会合が、17日、栃木県庁で開かれました。
会議は、カスタマーハラスメント、通称カスハラについて専門的な知見から防止対策を考えようと県が開催したものです。
委員は、県経済団体や労働団体、学識関係者など9人で構成されています。県内でも飲食店や自治体の窓口などで迷惑行為が問題となっていることから、県は2024年12月に「カスハラ」を防止する条例の制定に向け、検討を行う考えを示していました。
そのため2025年3月までに実態調査を行い、その結果、過去3年間にカスハラを経験したと回答した県内の労働者は、およそ4割に上ることが分かりました。男女別でみてみますと、男性が34.1%だったのに対し、女性が51.1%と半数以上でした。
また労働者が行政に求めるカスハラ対策として最も多かったのが、「防止条例の制定」で70%を超えています。
こうした結果を受けて、委員からは条例を早期に制定することや、カスハラの周知広報を広く行うべきだと意見が出ました。
会議は今年度あと2回開かれる予定で、2026年2月の県議会で条例案の提出を目指します。
会議は、カスタマーハラスメント、通称カスハラについて専門的な知見から防止対策を考えようと県が開催したものです。
委員は、県経済団体や労働団体、学識関係者など9人で構成されています。県内でも飲食店や自治体の窓口などで迷惑行為が問題となっていることから、県は2024年12月に「カスハラ」を防止する条例の制定に向け、検討を行う考えを示していました。
そのため2025年3月までに実態調査を行い、その結果、過去3年間にカスハラを経験したと回答した県内の労働者は、およそ4割に上ることが分かりました。男女別でみてみますと、男性が34.1%だったのに対し、女性が51.1%と半数以上でした。
また労働者が行政に求めるカスハラ対策として最も多かったのが、「防止条例の制定」で70%を超えています。
こうした結果を受けて、委員からは条例を早期に制定することや、カスハラの周知広報を広く行うべきだと意見が出ました。
会議は今年度あと2回開かれる予定で、2026年2月の県議会で条例案の提出を目指します。